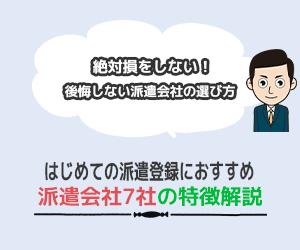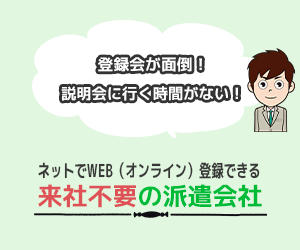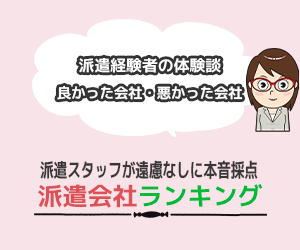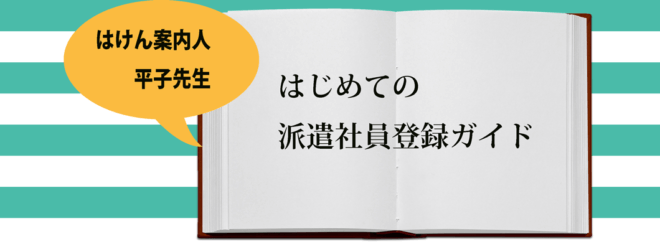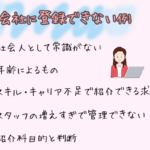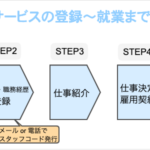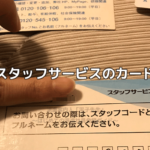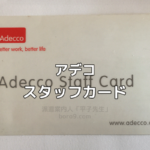派遣社員として働く為にも、派遣法を少し勉強しておこうと考えた楓ちゃん。しかし平成27年に行われた派遣法改正と2018年問題についていまいちよく理解できません。ここでは平成27年の派遣法改正でどのようなことが決定したのかを一緒に見ていきましょう。また2018年問題についても徹底解説致します。
2015年(平成27年)の派遣法改正まとめ 主な3つの改正
平成27年に決まった主な派遣法改正
- 特定労働者派遣事業の廃止。全て許可制に
- 専門26業務の廃止
- 派遣可能期間が個人単位と事業所単位に変化
1,特定労働者派遣事業の廃止、全て許可制に

「特定労働者派遣事業の廃止、全て許可制」は「一般派遣と特定派遣。廃止と許可制へ」で解説してもらったやつですね!
派遣会社は全て許可制に今まで派遣会社は「一般派遣」と「特定派遣」の2つのスタイルに分かれていたんだ。
特定派遣は簡単に言うと「常用型派遣のみを行う」派遣会社のこと。
「常用型派遣」とは、派遣会社と労働者が雇用契約を結んでから、派遣先に派遣されるスタイルのことだね。つまり派遣会社の契約社員として派遣を行う形だよ。
この場合、派遣先の仕事が終わっても派遣会社と労働者の契約は結ばれたままなんだ。
一般派遣は「登録型派遣」と、今説明した「常用型派遣」の2つを行う派遣会社のこと。
「登録型派遣」は始めに派遣会社へ登録を行い、派遣先が決定してから、一時的に派遣会社と労働者が契約を結ぶスタイルのことだね。一般的な派遣スタイルのことだよ。
つまり
特定派遣=常用型派遣
一般派遣=常用型派遣+登録型派遣
ということだね。
派遣会社が一般派遣を行うには、まず厚生労働大臣に許可をとる必要があるんだけど、特定派遣なら届出だけで行うことができる。
だから過去たくさんの特定派遣事業が誕生したんだけど、同時に悪質な派遣会社も生まれ問題になってきたんだ。
そこで平成27年の改正により、前者の「特定派遣」は全て廃止、派遣事業を行う為には必ず「許可」をとらないといけないというルールに生まれ変わったんだよ。
許可を得る為には、「専ら派遣を目的としていない」とか「キャリア支援や教育訓練の無償提供をする」とか条件があるし、指定された「基準資産額」や「事業所面積」を上回ってなければならない等、厳しい審査をクリアしないといけないんだ。
ちなみにいきなり「特定派遣事業を全て禁止!」とすると倒産する会社や、職がなくなる人がたくさん出るから、3年間の猶予期間が与えられているんだ。
それが2018年の9月30日で、これ以降完全廃止になるんだよ。
2,専門26業務の廃止
専門28業務の廃止専門28業務の廃止を理解する為に、まずは派遣の成り立ちについて簡単に説明するね。
実は大昔まで遡ると派遣という労働形態は日本では禁止されていた。これは派遣自体の仕組みが一時的に契約を結ぶものである為、労働者が不安定になる要素が多く、生活が脅かされる可能性があるからなんだ。
だから日本ではずっと派遣は禁止されていたんだけど、専門的技術を必要とするスキルなら、たとえ一時的な雇用であっても、次の仕事もすぐ見つかるだろうし、仕事にあぶれることも無いだろうと考えられるようになった。
そこで「専門的な28の業務」のみ派遣はOKというルールに変わっていったんだ。これが「専門28業務」。
しかしその後、数回法改正が行われ、28業務以外の仕事でも3年という期間限定なら、派遣しても良いという風に変わっていったんだ。これが「自由化業務」と呼ばれる仕事だね。
つまり派遣法改正を重ねる中で、「専門28業務なら無期限で派遣可能」+「その他の派遣は上限3年で派遣可能」という派遣の形に落ち着いたんだ。
ところが今回の平成27年法改正で、「やっぱり専門28業務という特別枠は廃止しよう」となって自由化業務と合体したんだ。
つまり専門28業務は、今後自由化業務の一員となるし、上限も3年になったということだね。
専門28業務について詳しくは「専門(政令)28業務」「自由化業務」とは。廃止と今後の派遣を参考にしてね。
3,派遣可能期間が個人単位と事業所単位に変化
個人単位と事業所単位今回の改正で新たに「個人単位」と「事業所単位」の上限3年というルールができたんだ。
「個人単位」は同じ事業所に3年以上派遣できないというルール。
つまり、楓ちゃんが2015年9月1日にA社の総務課に派遣され、働き始めたとしたら、3年後の2018年9月1日からはA社の総務課で働くことができないんだ。
他の会社であるB社なら働けるし、たとえA社でも他の課であれば、2018年9月1日以降も働くことができるよ。
「事業所単位」は派遣先である事業所が、3年以上派遣を利用してはいけないというルール。
つまり、さとる君が2015年9月1日から2018年9月1日までC社の大阪工場で働いたとしたら、2018年9月1日以降はC社の大阪工場では一切派遣の利用ができないんだ。
ポイントは、さとる君だけでなく、楓ちゃんや他の派遣社員も勤めることができないという点。C社の大阪工場では派遣自体が利用できないんだね。
ただし事業所単位での設定だから、同じB社でも大阪工場でなく兵庫工場なら派遣利用は可能だよ。
また「無期雇用派遣労働者」の場合や「60歳以上の高齢者」「産前・産後休業などの代替え業務」などは例外的に3年以上も可能だし、意見聴取した場合延長することも可能だよ。
詳しくは派遣の3年ルールとは?個人・事業所単位の抵触日を参考にしてね。
その他の改正 特定有期雇用派遣労働者への雇用安定措置
派遣元の責任今回の改正で、「特定有期雇用派遣労働者」に対して、派遣元が雇用安定措置を行いましょうというルールが義務づけられたんだ。
特定有期雇用派遣労働者とは「同一の派遣先で1年以上働いている人」で、なおかつ「契約終了後も継続して就業することを希望する者」を指すよ。
それらの人に対しては「派遣先への直接雇用の依頼」「新たな派遣先の提供」「無期雇用としての雇用を確保」「教育訓練や紹介予定派遣等、安定した雇用の継続を図るための措置」の内、いずれか1つの措置を努力するよう派遣元に義務づけられたんだ。
2018年問題とは
2018年問題専門28業務が廃止されたこと、そして上限3年の期間が設定されたことにより、法改正当時派遣で勤めていた人の上限3年が2018年9月30日にやってくる。
つまり2018年10月1日からは、今の派遣先を終了するか、派遣先で直接雇用されるか、派遣元で無期雇用されるかの3つの内どれかを選ばなくてはならないんだ。
でも現実的に考えて、派遣先がそんなにたくさんの人を正規雇用することはできないだろうし、派遣会社が無期雇用するのも今までより莫大なコストがかかる為、よほど良い人材でなければ避けたい。
結果、たくさんの人が今の派遣先を終了し、職を失うのではないかと危惧されているのが2018年問題なんだ。雇い止めの可能性が高くなるということだね。(雇い止めと派遣切り)
派遣労働者の安定の為に改正をした筈が、現状では逆効果になっているんだ。